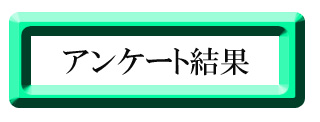「神経伝導検査について」
 日程:平成28年10月22日(土)14:30〜16:30
日程:平成28年10月22日(土)14:30〜16:30
場所: コンパルホール
内容:「神経伝導検査について」
講師:片山 雅史 技師(国際医療福祉大学 福岡保健医療学部)
参加者:31名
【研修会報告】
 今回は神経伝導検査(末梢神経と中枢神経)について基礎から波形、症状、注意点などを
国際医療福祉大学の片山雅史技師にご講演していただきました。
今回は神経伝導検査(末梢神経と中枢神経)について基礎から波形、症状、注意点などを
国際医療福祉大学の片山雅史技師にご講演していただきました。
内容として大きく分けて
1、末梢神経検査について
2、中枢神経検査について
末梢神経検査では
・機器のフィルターなどの基本設定をよく理解し使用する
・検査時、正中神経−尺骨神経吻合、副深腓骨神経などに注意する
・末梢神経障害の分類を理解する
・CTS重症例での痛みは反射などが影響している
・皮膚温度に注意する
中枢神経検査では
・刺激強度、加算回数について理解し使用する
・症状がある場所が病変とは限らないので徒手筋力テストや反射などを利用し位置を確認する
今回は末梢と中枢の広い範囲を2時間と短い時間に要約していただき、機器の基本設定や使用条件など
の復習、徒手筋力テストや反射などの補助診断の話も聞けて日頃の検査に役立てていける内容でした。
「日常の心エコーにおけるTips&Tricks」
 日程:平成28年10月15日(土)16:00〜18:30
日程:平成28年10月15日(土)16:00〜18:30
場所: ホルトホール大分 409会議室
内容:「日常の心エコーにおけるTips&Tricks」
講師:上運天 均 先生(大分県立病院 循環器内科)
参加者:35名
【研修会報告】
 今回は心エコーについて大分県立病院病院上運天 均先生に
今回は心エコーについて大分県立病院病院上運天 均先生に
ご講演していただきました。
内容として
1.基礎のおさらい
・Demensionの計測方法: LVセンターライン断面で、仮性腱索、SMTは避けて計測。
Mモード:leading-to-leading edge、 2D:trailing-to-leading edge。
・左室容量の測定、EFの算出、Teicholz法:Baseで計測。タコツボ、
心尖部肥大型心筋症、sigmoidに注意。
2.ASの心エコー
・ベルヌーイの定理、圧回復現象、ELCO補正、連続の式について
STJ(上行性大動脈)径小さい時は補正必要。弁口面積小さくなる。
LVOTO(左室流出路閉塞)はSVをRVOT、simpson法などで代用。
・AS評価にはplanimetry法が信頼性高い。
・Paradoxical lowflow AS:EF正常、LV小さい⇒循環血液量少ないのでA弁開かない。
流速、圧較差小さくでる。後負荷原因。
3、スキルアップのために・・・①症例提示(4症例) ②救急外来の心エコー
①症例提示:収縮性心内膜炎、Ebstein奇形、心房中隔瘤破裂、バルサルバ洞動脈瘤破裂
②救急外来の心エコー
・冠動脈支配領域について(LV segmention)
・心カテに入ることで心エコーでのSV、左室充満圧と比較でき意識づけとなる。
・低血圧の原因:循環血流、ポンプ機能低下、閉そく性病変。末梢血管拡張。
心エコーにおける基礎から応用まで教えていただきました。
計測方法、計測場所によってデータが大きく変わり、過小、過大評価になってしまうこと。
計測データで多くの情報が分かり、臨床に応用していけることを実感しました。
「動画を見て脳波を学ぼう」
日程:平成28年09月14日(水)19:00〜20:30
場所: ホルトホール大分
内容:「動画を見て脳波を学ぼう」
講師:石田 重信先生(あけのメディカルクリニック)
参加者:51名
【研修会報告】
今回はてんかんについての脳波の基礎から波形、症状、治療に至るまであけのメディカル
クリニックの石田重信先生にご講演していただきました。
内容として大きく分けて
1、てんかんの基礎、診断、分類
2、睡眠波形
3、動画でのてんかん症状の確認、治療など
・てんかんは必ずしっかり眠らせないと波形がきれいに描出されない事が多い
・てんかんは0〜1歳が最も多いがここ最近では60歳以上の高齢者にも増えてきている
・高齢者のてんかんは脳血管障害やアルツハイマー、頭部外傷などで引き起こされる事が多い
・動画にて全般発作や部分発作の違い、痙攣、硬直、失神に至る動きなどを確認した。
・実施の波形での左右差の確認の仕方(前頭葉てんかんの時は側頭葉の変化やゲイン調整)
・特発性の発作が部分性のもは小児期に多く思春期にはほぼ治癒する。
・治療としてバルプロ酸ナトリウムなどが使われるが職業によっては安全のため飲み続ける事が
多い(運転免許では2年間発作がなければ免許取り消しが復活できる可能性あり)。
今回は実際の症状などを動画で見る事が出来たので検査中の急な発作対応や検査する時の
問診の仕方など日頃の検査に役立てていける内容でした。
血液ガス検査
 日程:平成28年8月31日(水)19:00〜20:30
日程:平成28年8月31日(水)19:00〜20:30
場所: ホルトホール3階会議室
内容:「血液ガス検査」
講師: 三沢 泰一先生(ラジオメーター(株))
【研修会報告】
 今回の研修会はラジオメーター(株)三沢 泰一先生をお迎えしました。
今回の研修会はラジオメーター(株)三沢 泰一先生をお迎えしました。
先生には昨年に引き続き二回目のご講演となりました。
ご講演の内容は、
1、PH、CO2、HCO3-の関係
2、4パターンの酸塩基障害
3、酸素解離曲線の読み方
4、症例検討
など、基礎を中心にお話しいただきました。
特に、Henderson-Hasselbalchの式から、4つの酸塩基障害の見分け方の説明が
分かり易く、明日からの臨床に役立てたいと思います。
研修会は51名と多くの参加があり、血ガスへの興味の高さが伺えました。
とても勉強になった研修会でした。
定期的に血液ガス研修会を開催していけるように力を入れたいと思います。
心エコー 〜僧房弁閉鎖不全症〜 初級者編
 日程:平成28年8月10日(水)19:00〜20:30
日程:平成28年8月10日(水)19:00〜20:30
場所: アルメイダ病院 研修会館
内容:「心エコー 僧房弁閉鎖不全症について 初級者編」
講師: 梁井 恵子 技師(医療法人輝心会 大分循環器病院)
【研修会報告】
 今回は僧房弁閉鎖不全症の基礎から応用まで大分循環器病院の梁井恵子技師
にご講演していただきました。
今回は僧房弁閉鎖不全症の基礎から応用まで大分循環器病院の梁井恵子技師
にご講演していただきました。
内容として
1、身体所見(聴診、心電図、レントゲン)
2、僧房弁の解剖
3、僧房弁の形態変化(逆流)の原因
4、逆流の計測方法(重症度の評価)
5、心機能的評価
・身体所見では収縮期雑音Ⅲを聴取、心電図波形で左房負荷の確認、胸写で心拡大のチェックを!!
・僧房弁前尖、後尖の解剖的な成り立ちや違いの説明
・逆流の原因には弁の石灰化肥厚、腱索の異常など器質的変化、左室壁運動異常で起こる
機能的逆流があるということ
・計測方法においては重症度の評価には定性のみではなく volumetric法、PISA法、
Vena contracta法などの定量法は必須であり、症例をふまえて説明。
・心機能評価として、依頼目的、身体検査所見、弁の観察(弁接合は?逆流の偏位方向性は?)
左房、左室のバランスは? どこまで定量するべきか?などをふまえて評価するべきであり
弁膜症の評価、Ope適応、予後の判定はエコーでは決められないが、次へ進む治療、
診断へのとても有用な検査であるということ。
これらのことをふまえて検査することでよりステップアップしたエコー検査を行うことができると思いました。
血管診療認定技師について
ABI検査について
 日程:平成28年7月16日(土)14:30〜17:00
日程:平成28年7月16日(土)14:30〜17:00
場所: アルメイダ病院 研修会館
内容:「血管診療認定技師について
ABI検査について」
 講師: 黒瀬 孝二 技師(新別府病院)
講師: 黒瀬 孝二 技師(新別府病院)
一門 大典 先生(フクダ電子)
【研修会報告】
 今回の研修会は、血管診療認定技師について新別府病院の黒瀬孝二技師に、
ABI検査についてフクダ電子の一門大典先生にご講演頂きました。
血管診療認定技師においては、取得方法や実際の症例の動画を含め詳しく
ご説明して頂きました。
今回の研修会は、血管診療認定技師について新別府病院の黒瀬孝二技師に、
ABI検査についてフクダ電子の一門大典先生にご講演頂きました。
血管診療認定技師においては、取得方法や実際の症例の動画を含め詳しく
ご説明して頂きました。
ABI検査においては、CAVIやPWVについても丁寧にご説明して頂き、それぞれの 特徴や検査方法などよく理解することができました。 データのみで考えるのではなく、波形にも注目し結果の妥当性を追求することを 学びました。
また、実習を通して検査方法だけでなく検査が難しい患者様の対応方法など詳
しく教えて頂きました。
参加された皆様も血管診療認定技師とはどういった資格で、どのようにすれば取
得できるのか理解できたと思います。
また、ABIについては実習を通して普段かかえている問題など積極的に質問し、
今後の業務に活かせるのではないかと思いました。

心エコー〜大動脈閉鎖不全症〜初心者編
 日程:平成28年6月29日(水)19:00〜20:30
日程:平成28年6月29日(水)19:00〜20:30
場所: アルメイダ病院 研修会館
内容:「心エコー〜大動脈閉鎖不全症〜初心者編」
講師: 加藤 由希子 技師(アルメイダ病院)
上山 由香里 技師(大分大学医学部附属病院)
【研修会報告】
 認定超音波検査士の受験情報をまず伝えました。最新の受験資格や試験内容を
一昨年度受験した情報を元に行いました。
今回は初級者編でしたので、解剖、大動脈閉鎖不全症の定性・定量を
とても詳しく話しました。
認定超音波検査士の受験情報をまず伝えました。最新の受験資格や試験内容を
一昨年度受験した情報を元に行いました。
今回は初級者編でしたので、解剖、大動脈閉鎖不全症の定性・定量を
とても詳しく話しました。
定性・定量をする際の注意点もより詳しく丁寧に上山技師よりお話しいただきました。
前年度は心電図と照らし合わせた研修会を行いましたが、今回は手術適応に
対応できるところまで提示していて、わかりやすかったです。
循環器用薬と心電図
 日程:平成28年5月14日(土)14:30〜16:30
日程:平成28年5月14日(土)14:30〜16:30
場所: ホルトホール大分
内容:「循環器用薬と心電図」
講師:立川 洋一 先生(社会医療法人敬和会大分岡病院)
【研修会報告】
循環器用薬と心電図についてご講演頂きました。 病態ごとの循環器薬の選択、種類の多い抗不整脈について詳しく教えて頂きました。 抗不整脈薬ではⅠ群からⅣ群に分類されるVaughan Williams分類の各作用機序に ついて詳しく理解することができました。 また、循環器用薬の使用により既存の不整脈が増悪してしまう、催不整脈作用について 徐脈性・頻脈性とお話し頂きました。薬が心電図のどこに作用し、どのような効果が 得られるかをよく理解することが大切だと再認識しました。また、一つ一つの心電図に ついても、とても丁寧に分かりやすくお話して頂きました。
研修会報告 一覧表
| 日 時 | 研修会名(テーマ) | 講 師 | 場 所 | 参加者 |
| 2017.02.01 |
心エコー 〜僧帽弁狭窄症・大動脈弁狭窄症〜 |
大野 主税 (大分岡病院) |
ホルトホール大分 | 41名 |
| 2017.01.18 |
呼吸器機能検査の進め方 | 佐野 成雄 技師 (大分大学医学部附属病院) |
ホルトホール大分 | 69名 |
| 2017.01.13 |
腹部エコー | 岡庭 信司 先生 (飯田市立病院) |
ホルトホール大分 | 61名 |
| 2017.01.12 |
甲状腺エコーの症例検討 | 谷 好子 技師 (野口病院) |
野口病院 | 29名 |
| 2016.12.10 |
超音波検査について | 乙迠 賢一 氏 (日立製作所) |
アルメイダ病院 | 35名 |
| 2016.10.22 14:30〜 |
神経伝導検査について | 片山 雅史 技師 (国際医療福祉大学 福岡保健医療学部) |
コンパルホール | 31名 |
| 2016.10.15 16:00〜 |
日常の心エコーにおけるTips&Tricks | 上運天 均 先生 (大分県立病院 循環器内科) |
ホルトホール 409会議室 |
35名 |
| 2016.09.14 19:00〜 |
動画を見て脳波を学ぼう | 石田 重信 先生 (あけのメディカルクリニック) |
ホルトホール |
51名 |
| 2016.08.31 19:00〜 |
血液ガス検査 | 三沢 泰一先生 (ラジオメーター(株)) |
ホルトホール 3階会議室 |
51名 |
| 2016.08.10 19:00〜 |
心エコー 〜僧房弁閉鎖不全症〜 初級者編 |
梁井 恵子 技師 (医療法人輝心会 大分循環器病院) |
アルメイダ病院 研修会館 |
44名 |
| 2016.07.16 14:30〜 |
血管診療認定技師について ABI検査について |
黒瀬 孝二 技師(新別府病院) 一門 大典 先生(フクダ電子) |
アルメイダ病院 研修会館 |
36名 |
| 2016.06.29 19:00〜 |
心エコー〜大動脈閉鎖不全症〜 初心者編 |
加藤 由希子技師(アルメイダ病院) 上山 由香里 技師(大分大学医学部附属病院) |
アルメイダ病院 研修会館 |
48名 |
| 2016.05.14 14:30〜 |
循環器用薬と心電図 | 立川 洋一 先生 (社会医療法人敬和会大分岡病院) |
ホルトホール大分 | 56名 |